目次
はじめに
「履歴書って、どこまで真面目に書けばいいの?」
「毎回同じ内容で出してるけど、通らない…」
そんな声、これまで何十人もの転職相談の中で何度も聞いてきました。
かく言う僕も、最初の転職では5社連続で書類落ち。自分なりに「ちゃんと書いたつもり」だったのに、音沙汰すらない……。正直、何が悪いのかさっぱり分かりませんでした。
でも、たった3つのコツを意識しただけで、書類通過率がぐんと上がったんです。
この記事では、僕自身や友人たちのリアルな転職経験をもとに、「履歴書で損しないための書き方」をわかりやすく解説します。

書類通過率を上げるには、履歴書に“自分の意図”を反映させること
まず前提として、履歴書って「形式的なもの」と思われがちなんですが、実は全然そんなことありません。企業側は、履歴書の一文一文から“あなたがどういう人か”を読み取ろうとしています。
よくあるNGパターンはこれ:
- 「とりあえず空欄なく埋めた」だけの履歴書
- どの企業にも同じ文章で出している
- 自己PR欄がありきたりで、読んでも印象に残らない
これ、正直に言ってしまうと、相手の心に何も刺さらない履歴書になってしまうんです。
では、どうすれば「この人、ちょっと会ってみたいな」と思ってもらえる履歴書になるのか?
ポイントは3つです。
ポイント①:「志望動機」は“企業に語りかける”ように書く
意外と多いのが、「なぜその企業なのか」が伝わらない志望動機。
たとえば、NG例はこんな感じ:
御社の企業理念に共感し、社会貢献性の高い事業に惹かれたため志望いたしました。
──ありがちですが、どこの企業にも出せる内容ですよね。
◎改善するには?
まず、企業のWebサイトを見て、
「どんな取り組みがあるのか」「どんな人材を求めているか」を調べましょう。
そして、その内容に自分の過去の経験や価値観をどう重ねられるかを言葉にしてみます。
実例:
御社の「現場目線でサービスを改善していく」という方針に共感しました。前職でも、顧客アンケートを活用して現場改善に取り組み、結果として導入後のクレーム数を30%減少させた経験があります。この経験を活かし、御社のカスタマーサポート向上にも貢献できると考えております。
このくらい具体性があると、読み手にも「この人、自社をちゃんと見てるな」と伝わります。
ポイント②:「自己PR」は“数字+行動+結果”で組み立てる
履歴書の自己PR欄、どうしても抽象的な表現になりがちです。
「コミュニケーション力があります」「責任感があります」
→ 伝わるようで、伝わらない。
◎どうすればいい?
僕がよくおすすめしているのが、「数字+行動+結果」の型。
例:
前職の販売職では、前年比120%の売上アップを達成しました。
具体的には、売れ筋商品の売場改善や、POPの文言を変えるなど“お客様目線”での提案を行い、1日あたりの購買数を平均5点→8点に向上させました。こうした数字に基づいた工夫は、今後の職場でも活かせると考えています。
これ、ほんの数行ですが、「実際に何をしたのか」が一発でイメージできるんですよね。採用担当者は、そういう“仕事ぶり”を履歴書から読み取ろうとしています。
ポイント③:「写真・手書き・レイアウト」も、実は侮れない
これ、意外に見落とされがちなんですが、見た目の印象も選考に少なからず影響します。
- 証明写真が古い or 笑顔ゼロ → 「やる気なさそう」に見える
- 手書きで雑な字 or スキャンが薄い → 「丁寧さに欠ける」印象
- レイアウトが詰まりすぎていて読みづらい →「読む気が失せる」
たとえば僕の友人Cは、見た目を見直しただけで、書類通過率が2割→5割超に上がったんですよ。何をしたかというと:
- コンビニの証明写真→スタジオで撮影(3,000円くらい)
- Wordで整えたレイアウトをPDF化
- 手書き欄は丁寧に
見た目の丁寧さって、やっぱりその人の仕事への姿勢にもつながるんですよね。
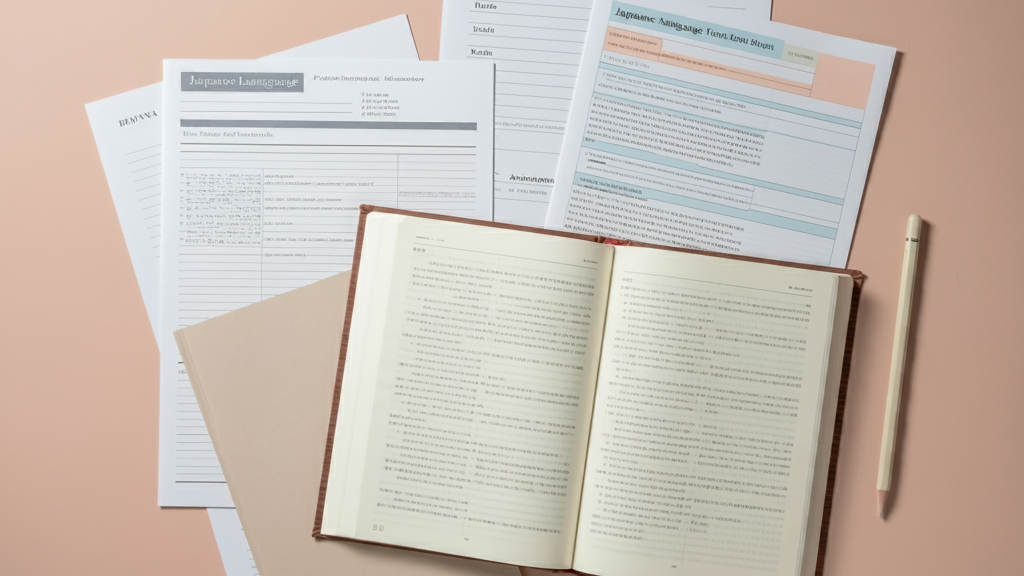
まとめ:履歴書は“自己紹介ツール”じゃなく、“プレゼン資料”
履歴書は、ただの情報集じゃなくて、「自分がこの会社に必要な理由」を伝えるプレゼン資料です。
最後にもう一度、3つのポイントをおさらいすると:
- 志望動機は「企業の個性」に語りかけるように書く
- 自己PRは「数字+行動+結果」で“何をしたか”が伝わるように
- 見た目(写真・字・レイアウト)も手を抜かない
「履歴書は苦手」という人ほど、実は伸びしろがあります。
あなたの想いと経験を、“伝わるカタチ”に整えるだけで結果は変わる。
まずは1社分、丁寧に作ってみてください。きっと、通過率は変わってきますよ。

